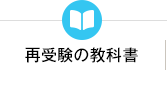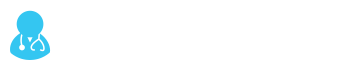医師として働くには、国家資格を取得していることが絶対条件です。資格を取るためには医学部を卒業する必要があり、免許取得をした後も2年以上の研修を受けることが義務付けられているので、一人前の医師になるまでの最短期間は決まっています。
医者になるまでの最短期間と年齢
医者として活動するには、国が認可した医師国家免許を取得していることが大前提です。もちろん免許なしに医療行為を行った場合は犯罪となりますので、必ず免許を取る必要があります。では医師国家免許はどうすれば取得できるかというと、大学の医学部や医科大学を卒業していることが受験の条件。医学部は6年制ですから、医師国家免許を取得できるまでは、最低で6年かかることになります。
医師国家免許を取得すれば医療行為は行えますが、免許取得したばかりの医者は臨床経験が皆無ですから、免許取得後に医療現場で研修医として2年以上の経験を積むことが法律で義務付けられています。大学病院などで内科や外科、小児科などさまざまな診療科をローテーションで経験し、上級医や指導医の下について、患者の治療にあたります。
研修期間が終了すれば、ようやく医者として単独で患者を担当できるようになります。通算すれば、医学部に現役合格して18歳で入学し、卒業後に医師免許をストレートでパスした後、2年間の研修を終了すれば、高校卒業から最短で8年、26歳で医者として独立できる計算になります。
一人前と呼ばれる年齢
しかし、最短で医者になれても「一人前」かと言われれば、疑問符がつくかもしれません。最近では義務化されている2年間で研修を終える人は少なく、さらに研鑽を重ねるため3年目以降も研修を続けるのが一般的です。
免許取得後の1~2年は初期研修、または前期研修と呼ばれ、研修医(レジデント)としてさまざまな診療科での経験を通して、自分の進みたい診療科を決めます。その後、3?5年は後期研修医(フェローシップ)として選択した診療科で担当医師から指導をあおぎ、専門分野での実績を積みます。
この後期研修期間に進みたい科の認定医や専門医としての資格を取得し、ようやく一人前の医者と認識されることが多いようです。
免許取得後の4~5年間を研修期間と考えると、一人前と呼ばれるには高校を卒業して約10年、年齢にすると30歳前後となります。ただ、一生研鑽を積む必要がある医者という仕事において「一人前」の定義は非常にあいまいで、人によって考え方は異なります。あくまで目安として高卒後10年、と考えておきましょう。
開業医になる平均年齢
研修期間を終えた後の進路は人それぞれで、大学病院に残る人、中小規模の病院に勤務する人、大学で研究職につく人、実家の病院を継ぐ人、開業する人など、さまざまなケースがあります。
医者になるからには、自分が考える理想の医療をめざして開業したいという夢を持つ人も多いことでしょう。また最近では医師不足などの諸問題から、病院の勤務医や研修医としての勤務は相当ハードだと言われています。当直が多い肉体的な疲労や、人間関係などによる精神的ストレスから、疲弊して開業を考える人も少なくないようです。
ただし開業医になるには医者として知識と経験を積むだけでなく、開業するための資金や不動産の確保、経営スキルの養成など医学以外の知識や財力が必要になるため、ある程度の年齢になってから開業するのが一般的な流れといえそうです。
日本医師会が会員を対象に行った開業医の実情に関するアンケート調査によると、病院または診療所を新規開業した医者の平均年齢は41.3歳であることがわかりました。高卒後から計算すると、医学部、研修医時代を経て、他の病院や医療機関で10年以上のキャリアを積んだ後にで開業していることになります。
医師になるのに年齢は関係ない
2018年4月入学において、国公立大だけで26,033人が受験。合格者が4,401人、平均倍率は5.9倍と狭き門です(後期日程だと14.8倍)。
定員割れしても一定以上の学力がないと合格できない学部なので、たとえ落ちたとしても医者になりたいという強い思いを持った学生たちは何度でもトライします。
また、一旦社会に出てから医者を志す人もいます。夢を思い出した、家族の介護がきっかけになった、ドラマの影響など理由はさまざまですが、医者になるために相当な情熱が必要なのは言うまでもありません。大事なのは情熱で年齢ではないのです。
年齢よりも経済や体力的な理由
医者を目指すのに大事なのは情熱ですが、若いに越したことはありません。
一番に挙げられるのは、経済的なサポートでしょう。社会人でも奨学金を申し込むことはできますが受かるとは限らず、教育ローンの利息もかなりのものです。比較的申請が受理されやすい学生が有利です。
また体力的な問題も大きいです。研修に入ると自分の時間がもてないほど忙殺され休む間もなく次の実習に移るなど、とにかく体力が必要になります。回復力の早い若いうちに医者になるのをおすすめします。
医学部の入試科目について
国公立の場合は募集人員の66%を前期日程、残りを後期日程で合否判定をするそうなので、前期日程での受験が有利と言えます。
国公立ではセンター試験5教科7科目を実施。前期では英・数・理と面接、後期では小論文や総合問題、面接も行います。中には学科試験を課す大学も。私立大学では英・数・理2・小論文・面接を基本としている大学もあります。
これだけの科目でコンスタントに85%以上の得点率をあげるのはとても困難。それなりの作戦をたてて勉強する必要があります。ここでは教科ごとに進め方や、参考書の選び方などをまとめてみました。
医学部受験における英語
英語は医学部受験の中でもかなり重要な科目です。他の科目によほど自信がない限り、苦手なままにしておくと医学部合格は難しいでしょう。医学部の入試試験では、長い英作文の作成や過度に難しい文を訳させられることはありません。基礎を身につけ、英文を読む力を身に付けるのがポイントです。数学で公式を知らずに問題が解けるようにならないのと同様、英単語と文法は暗記する必要があります。
まずは、たくさんの単語の暗記と文法の理解から目指しましょう。暗記は短期集中で一気に暗記するのがおすすめ。どんなに丁寧にやっても時間をかけすぎると、頭にも残りづらくなります。文法は半年ほどかけてじっくり暗記するとよいでしょう。また一度暗記しただけでは忘れてしまうため、適度に復習することも大切です。人気の参考書として、英単語には「DUO」や「速読英単語」、文法では「ネクステージ」「基礎英文問題精講」がよく使用されています。
医学部受験における数学
数学は最も差のつきやすい科目です。数学で得点を取るためには、基礎力がとても重要となります。ただ公式を暗記して当てはめて回答するという方法では、解けないときの解決方法がわからなくなるケースも。公式や計算する上で「なぜその解答方法になるのか?」を考え、理解することで応用問題にも対応できます。基礎となる計算力や理解力、本質を理解できないまま応用問題にチャレンジするのは時間の無駄になるでしょう。
一夜漬けの丸暗記で成績が伸びる科目ではなく、長く時間をかけて基礎をマスターすることが求められます。はじめのうちは講義型参考書「理解しやすい高校数学」で、公式や解き方について理解を深めるのがおすすめです。基礎問題を習得するものは、「基礎問題精講」に定評があります。
医学部受験における国語
センター受験で必要になる国語の勉強は、優先順位を明確にして取り組むのがおすすめです。国語に時間を費やしすぎて、他の教科がおろそかになってしまったという受験生も少なくありません。医学部の受験においての優先は数学・英語・理科の次に、国語・社会です。国語で高得点を取ることができれば、大きなプラスになります。中でも暗記で点数を狙いやすい古文や、漢文を優先するのがポイント。
一方、現代文にたくさん時間をとって勉強しても高得点が取れない可能性があるので気を付けましょう。「読み解き古文単語」「漢文ヤマのヤマ」などが、定評のある参考書です。
医学部受験における理科
理科の中でも、化学・物理・生物とそれぞれの科目によって対策の方法は異なります。その3つに共通するのは、基礎をしっかり理解することです。なぜそうなるのかという本質がちゃんと分からないまま化学や物理の難しい問題にチャレンジすると、時間の無駄になってしまうでしょう。
生物は幅広く正しい知識を身につけることが大切。細かく掘り下げるとキリがないため、受験に必要な知識を選別するのがポイントです。多くの入試では、3つのうち2つを選択することになります。ほとんどの受験生は化学を選び、もう1つを物理か生物で迷うようです。自分は何が得意なのか先生や講師と相談しながら決め、それぞれの科目にあった対策をしましょう。参考書は基礎的な学習ができるものがおすすめです。
医学部受験における地歴・公民
医学部受験における地歴公民の点数は大学によって配点が違うものの、900点満点中およそ100点と言われています。
地歴公民は大きく分けて4つの大分野に分かれています。
- 1.日本史・世界史
- 2.地理
- 3.政経・現社
- 4.倫理
更に細分化すると、世界史Aや世界史B等も含まれます。記憶する量が膨大なので、なかなか力が入らないという人もいるはず。記憶型の勉強方法になりがちな地歴・公民ですが、絶対に押さえておきたいポイントが3つあります。
1つは知識量と演習量が最も多いとされる地理です。地理は難しそうに見えますが、日本史や世界史と密な関係があります。そのため、まず先にやるべきは地理、日本史・世界史でしょう。この2つを覚えると、政経・現社と倫理の知識が自ずとつきます。また世界史と日本史どちらを先に勉強するかは人によって異なりますが、世界史から勉強すると全体像が見えてきてスッキリ頭に入ってきます。
しかし、世界史は色々な国が出てきて頭の中に知識があふれて、わからないという人もいるでしょう。そんな人におすすめの本が「一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書」です。推理小説を読むように世界史にのめり込めるので、詰め込みがあまり得意でない人でも頭の中に内容がすらすら入ってきます。
医学部受験における小論文
医学部受験における小論文は出題形式・テーマにより多種多様な切り口から問題が出題されます。傾向は以下の通りです。
- 1.課題文読解型問題
- 2.図表分析型問題
- 3.テーマ型問題
- 4.理科論述型問題
- 5.総合問題
- 6.英文問題
課題分読解型問題では、ある課題に対して見解や要約を求める問題が出題されます。例えば医者とは何か?や、死生観です。つまり医者と人間の本質に迫る資質を試そうとするものが多く、知識の専門的な部分を狙って出題していないため日頃から経済誌や科学雑誌、医者とは何かという事に関する記事を読んでおくとクリアできるでしょう。
図表分析型問題はグラフの表の傾向を読み取り、人口動態やこれから起きる問題について自分の見解を述べるものです。日頃からグラフや、表の読み取りをする必要があります。また毎年厚生省から発行される「図説 国民衛生の動向」は必読です。テーマ型問題では資料は原則としてなく「~について述べなさい」という論述のテーマだけが示され、時事系の予備知識が必要とされます。NEWSWEEKといった社会系雑誌の利用がおすすめです。
理科論述型問題では物理・化学・生物の理科3科目に加え、数学の知識が必要となり、発想力を問われる問題が出題される傾向があるようです。理科論述型は入学する医学部によって問題が異なるので、過去問題を数多く演習する方法が効果的といえるでしょう。
総合問題は1つの論文の中に英・数・国・理・社の各要素が盛り込まれた、バランス型の問題です。相応の学力が必要とされますが、勉強しておくことで対策はできます。
論文の中でも一番の難関となるのは、英文問題です。英文は日々の生活から英語に慣れ親しんでいなければ正直全く分かりません。対策方法は、医学系英文雑誌をたくさん読む、多読をして量をこなす方法がありますが、まずは後者の方を試してみてはいかがでしょうか。英語の悩みを解決する「英語多読 すべての悩みは量が解決する!」は参考書としておすすめです。
医学部受験における総合問題
総合問題は、1題の中に英・数・国・理・社の各教科の要素が盛り込まれた問題になります。または各教科の問題が数問組み合わされた問題群です。医学部受験では、数学や理科の問題が多い傾向にあります。それぞれの教科の高い点数が必要となるので、各教科のポイントをおさえて学習をしっかり積んでいきましょう。
医学部受験における面接
医学部の面接は難しいと想像してしまうでしょう。難しい用語を交えた質問と、回答が飛び交う面接場面が容易に想像できます。人の命を救う仕事ですので、実際に専門的な知識を必要とするのが特徴です。しかし実際の面接ではその人が医師としてやっていけるかどうかが重要視されます。
例えば、態度の悪い医者を信用できるでしょうか?また、態度が良くても会話が成立していない医者に頼りたいと思わないはずです。面接ではこうした常識的マナーが試されます。面接対策では特別な対策は必要ありませんが、人と対面する際のマナーを知っておきましょう。常識だけにとどまらず、医療関係における話題をチェックしておきましょう。
医学部受験・面接の口コミ
【入学年度】2016年
接官は2人です。面接の流れは15分くらいなのですが穏やか過ぎて、逆に取る気がないと終始不安でした。メディアを通じて全国的な医師不足という事実を知り、医師不足の解消
はもちろん、患者さんに寄り添いたいと思っています。面接対策では、予備校に通うことにしました。週に1回コツコツ面接対策を実施。複数の参考書を使用して、できるだけ広い視野を持つことを心がけつつ、先生と1つの話題を提示し、それについて掘り下げ合いながら意見を深めました。医療関連だけでなく政治や経済面もチェックし、見識を広げ自分なりの考えをまとめました。
【入学年度】2017年
面接では自分の思っていることを論理的に伝えるように心がけました。面接時間は10分程。医学に関する知識がないと面接官の質問を理解できるか不安でしたので、気になった医学の専門書を読んだり、予備校の先生に聞いてみたりしました。ちょうど予備校の先生がボランティアで医療関係の基礎知識を教えてくださるという事でしたので、とても有り難かったです。また、気になる問題をメモに取り、自分の考えをまとめる事もしました。
医者になった際はたくさんの患者とお話しする機会がありますので、相手の話した意図を正確に理解する事が大事だと思います。
【入学年度】2017年
面接官に「医師に必要な資質はなんですか?」と聞かれた時、「1つはマナー、もう1つは患者さんとのコミュニケーションです」と答えました。もし技術力があっても、態度の悪い医者を患者さんは信頼してくれるでしょうか。また、患者さんの言っている事が理解できず、「わからない」と答えてしまう医者を信頼する患者さんはいないと思います。知識だけに頼るのではなく、患者さんとのコミュニケーションを大事にすることが医者になるための近道なのではないかなと思っています。日頃から情報に敏感になることで、色々な人とコミュニケーションが取れるようになるはずです。
【入学年度】2015年
面接時間は15分程です。4人の面接官に囲まれながらも、雰囲気はゆるやかでした。面接対策は予備校で過去の質問をあさり、どの質問にも対応できるように。また、言葉遣いに気を付け、身なりは清潔さを出すように心がけました。面接時は緊張しましたが、先生方のほうから答えやすい雰囲気をつくってくださるなどの配慮があり、自分の意見を述べる事ができたので良かったです。その経験もあって医者になるにあたり、患者さんには不安を与えないように雰囲気づくりも大切だと思っています。
【入学年度】2016年
両親が医師で一番身近に感じていた事もあり、幼い頃から自分も医師になるのだろうと感じていました。沖縄県事態に魅力を感じていたわけではありませんが、なるべく早く医師として活動したかったので、身の丈にあった大学を選びました。高校時代は週1ペースで予備校に。静かで勉強したい人が集まっているなと記憶に残っています。わかりやすい授業を受けつつも自分なりに勉強していく姿勢を講師の方から学ぶことができました。最短で医師になるには、自分のできる範囲を知っておく事が必要だと思います。
まとめ
他の学部と比べると医学部の受験は狭き門です。合格するには得意分野だけでなく、各教科をしっかり学習しなければいけません。限られた時間の中でどれだけ効率よく勉強し続けるかが大切です。受験の傾向と対策を効率よくつかむためにも、医学部予備校を活用しましょう。受験対策や勉強方法を熟知している予備校なら、効率よく学べるはずです。また、同じ目標を持った仲間やサポートしてくれる先生がいることで、モチベーションアップにもつながります。
有名講師で選ぶ医学部予備校
-
画像引用元:https://www.medical-labo.com/cp/lecture/lecture_2.html
可児先生のいる
メディカルラボ
著書多数の実力派講師が授業を担当
「あなたの医学部合格をかなえる成功の9ステップ」をはじめ、医学部受験についての著書を多数執筆。
-
画像引用元:https://integra-edu.jp/lecturers/
清水先生のいる
INTEGRA
NHKにも協力する教育全般のプロ
慶応、順天堂、聖マリアンナ大など数々の大学での指導実績を持ち、その指導歴は26年を誇るベテラン講師です。
-
画像引用元:https://keioshingakukaifrontier.com/teachers/
橋本先生のいる
慶応進学会フロンティア
TV出演多数の講師が教える受験