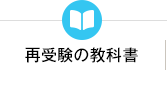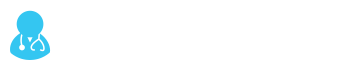医学部受験生にとって、筆記試験以外の大きなハードルとして頭を悩ませる面接試験。この面接試験は現役受験生や、社会人から医学部合格を目指す再受験生にとっても大きな課題となっています。
しかし、現役受験生と再受験生での面接の内容はどのように変わってくるのでしょうか。
ここでは、医学部再受験生の面接試験や現役受験生との面接内容の違いについて、詳しく解説していきます。
再受験生と現役生の評価はどのように分かれるのか

二次試験には小論文や面接など、医者としての適正や洞察力、道徳観念などの内容まで、さまざまなものが含まれます。評価そのものがどのように分かれるのか、分かれないものなのか大学によっても異なりますが、一般的に「再受験に寛容」とされる大学と再受験に厳しい大学とでは、評価は大きく異なってくるでしょう。
再受験に寛容な大学では年齢制限を設けてはいないことがあり、厳しい大学ではある一定の年齢を超えると合格が難しいことが多いとされています。再受験に寛容な大学では多くの場合、現役生にはない「社会経験」や「人生経験」を評価してくれることが多いのです。
再受験に寛容とされる大学について
東京大学や九州大学は、寛容であるばかりか一般入試に面接試験そのものがないのです。 このために再受験者の狙い所ではあるのですが、特に東大理Ⅲは極めて難関であり、九州大学医学部も偏差値70を超えるために、合格はかなり難しい大学とされています。
他に国立大学では滋賀医科大学や、三重大学、奈良県立医科大学について、東京大学・九州大学と比較すれば偏差値的に狙いやすく、再受験生の合格者も毎年多く排出しているので、再受験者にとってオススメできる医学部といえます。特に滋賀医科大学は、形式のみの面接であって学力を最重要視するとされていることから、経歴に空白期間が存在している・自信がないという場合には、よい選択肢となるといえます。
私立大学では、杏林大学、帝京大学、日本医科大学などが再受験生や多浪生に寛容な大学として挙げられています。
その他の再受験に寛容な大学については下記ページでもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
『再受験に向いた大学情報』を見てみる
面接の点数はどのくらいなのか
面接の点数といっても具体的に明記している大学はほとんどないでしょう。
医学部における面接点の点数配分は、時代によってしているために、「全国医学部最新受験情報」などで、最新情報を確認し情報収集しておくことが重要です。
情報収集によって合否が決まるともいえますので、医学部受験は情報戦であることも頭に入れておいたほうがいいでしょう。
回答するときの姿勢や注意点とは
 学力試験に過去問があるように、面接試験にも傾向があるとされています。
学力試験に過去問があるように、面接試験にも傾向があるとされています。
この傾向ばかりに気を取られていてはいけないのですが、手に入る情報は最大限に活用しましょう。
最も面接試験で聞かれる事項について、
- 医師の志望動機
- 大学の志望動機
- 自分自身が医師に向いていると思うか
- 自分の長所と短所について
- どのような医師になりたいか
- 将来の目標 など
医学部入試ならではのことも多く含まれます。ここに挙げたものはほんの一例に過ぎません。
しかし、多くの大学入試で聞かれている項目でしょう。これらの内容を質問されたとき、事前に準備しないで瞬時に回答できる方は多くはないのではないでしょうか?
特に再受験生にとって、面接試験の対策として頻出問題に対して自分自身の言葉で回答を用意しておくことが重要です。
事前に準備をする
再受験生であることを意識して回答例を作ることは、とても大切です。
自分の経歴や経験にもとづいて、有利に働きそうな要素をチョイスしていきましょう。
例えば、会社で海外赴任をした経験があることでコミュニケーションスキルが上がった(外国語など)、世界情勢について詳しくなったなど、アピールできそうな内容は回答例に盛り込んでいきましょう。
ここでは自分自身をポジティブに分析し、自身の考え方や気持ちを振り返ることが重要です。
再受験であることに負い目などを感じてしまう人もいるのですが、心の中で思っても口に出さないことも必要です。私なんか……などのネガティブな思考は避けるようにしてください。
4軸で想定される質問内容をまとめる
4軸とは
- 自分のこと
- 家族からの理解
- 社会への貢献度
- 友人・知り合いなど
です。
自分のことや家族のこと、友人・知り合い、また、社会への貢献度について答えられるようにしておいてください。想定される質問をエクセルなどにまとめておくとわかりやすいでしょう。
要点を書き出してから、自分の言葉を文章で表現してください。箇条書きで書いておくと、いざ言葉にしようとしたときに、文章として口から出てこないなどのアクシデントにつながってしまいます。ですので、文章にしてから口に出して言ってみる練習をするのもいいでしょう。
回答するときの姿勢や注意点とは
ここで紹介する内容はとても重要な質問なので、必ず回答例を考えておいたほうがいいでしょう。
なぜ社会人になってから再度医学部を目指し始めたか
ここでは医師になろうと思ったキッカケを聞いています。社会人になってからということにポイントを置いて、ご自分の中で医師を志したキッカケを述べましょう。
なぜ現役で目指さなかったのか
現役の頃に何を目指したのか、医師という選択肢がなかった理由などを挙げるといいでしょう。この質問は、医師になるキッカケにもつながるので大切にしましょう。
不合格だった場合、何歳まで目指すのか
このような意地の悪い質問もあるかもしれません。そういった場合にも備えておいたほうがいいです。
ここでは、「合否を確認した後、自分自身に諦めるのかを聞いてみます」、「生涯現役で頑張りたいです。諦める気持ちが起こったときに考えます」などできるだけポジティブに取れる内容で乗り切りましょう。
自分で台本を作るような気持ちで!
 面接試験では緊張してしまい、自分の意見や思いを上手に伝えられるのか不安になることでしょう。
面接試験では緊張してしまい、自分の意見や思いを上手に伝えられるのか不安になることでしょう。
筆記試験の勉強で何回も問題を解くように、面接試験の演習を何回もしておくような勉強法をおすすめします。何回も予行練習しておくことで、気後れや緊張をほぐすことにつながるはずです。この質問にはこういう回答を用意した、というような気持ちに余裕が生まれます。
最初の質問がうまく回答できると、言葉が口から滑らかに出てくる可能性も高まります。
ご自分で面接試験という舞台の台本を作るような気持ちになって、面接官が聞いてきそうな質問を書きだし、自ら答えることをしてみてください。また、予想外の質問をされた時でも慌てないようなメンタル面の強化をしておきましょう。
医学生や医師になったときにも強い精神力は力になりますよ。