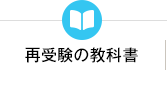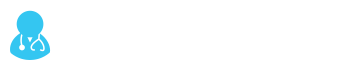いよいよ入試が近づき、予備校の先生と相談のうえ、自分の学力に合わせて志望校をしぼりこんだ秀一。過酷な受験戦争を勝ち抜いて、待っていたのは念願の医学部! 現役生で失敗したときと、何が違っていたのか? 医学部合格の勝因を探りつつ、あこがれのキャンパスライフに向けて着々と準備を進めていく。
医学部合格!体験者から勝因をさぐる

医学部に合格した人の話を聞くと、やみくもに勉強するのではなく、志望校合格に照準を絞って勉強するべき内容をしっかりと見極め、メリハリをつけて勉強したケースが多いことがわかります。
<医学部受験に合格した人の体験談>
「現役時代は入れるならどこでもいいと思っていましたが、浪人になってからは志望校を決めて対策を入念に行いました」
「少人数制の予備校を選んで通いました。わからないことをその場で確認できることや、不安や愚痴にもつきあってもらえたことで勉強に専念できたのがよかった」
「ダラダラ勉強するのではなく、限られた時間に集中的に勉強するようにしました。苦手な科目は徹底的に繰り返して少しずつ克服しました」
医学部に合格したら

合格を掴む!医学部予備校選び
超難関の医学部受験を見事クリアしたら、入学手続きを行います。複数校に合格した人は、どの大学に入るか早急に決めて、すみやかに手続きを取りましょう。
医学部は卒業までに6年かかりますので、他の学部に比べて学費がかかります。国立の場合は年間にかかる学費が他学部と変わりませんが、私立の場合は6年間の学費総計が2000~5000万円かかると言われています。在学中の生活費なども考えて、経済的に支援が必要な人は奨学金や教育ローンなどの申請も忘れず行いましょう。
親元を離れて学校に通う人は、アパートや学生寮など生活場所の確保も必要となります。医学部に入っても勉強漬けの忙しい日々が続きますので、1日も速く医者になるには勉強に専念できる環境づくりも大切にしたいところ。パソコン、第二外国語用の電子辞書など、学生生活に必要なアイテムも余裕のあるうちに用意しておくのがよさそうです。
医者はカラダが資本。食生活の乱れは学生生活に支障をきたします。外食やコンビニ食でOKなどと考えず、手料理のレパートリーを増やしておくことも大切です。
医学部合格後から医者になるまでの道のり
超難関の医学部受験をクリアしたからといって、勉強はこれで終わりではありません。医療業界では常に新しい治療法や新薬が開発され、一生勉強し続ける仕事といえます。
医学部も、実は受験より入学してからのほうが勉強が大変だといわれます。一般教養はもちろんのこと、分子・細胞レベルから人体、精神、社会、宇宙に至るまで、幅広い知識を身に付けることが求められます。5~6年には臨床実習を積んで実践力を養っていきます。留年も珍しくない厳しい学生生活ですので、気を抜かずにがんばっていきましょう。
卒業と同時に医師免許を取得すると、大学付属病院などで研修医として2年間みっちり実地トレーニングを積むことになります。ここはいわゆる医者の見習い期間。さまざまな科を体験して、最終的に進む診療科を絞っていきます。
2年間の研修が終われば、はれて1人前の医者に! 大学病院に残るか、開業医になるか、医者としてどう生きたいかによって、進路を選ぶことになります。
医学部の志望校はどう決める?
国公立か私立かを決める
全国に82校もある医学部。志望校はどこにすべきか、何を基準に選ぶべきかわからない人もいるのではないでしょうか。ここではまず、国公立大学と私立大学の医学部試験の違いや特徴を説明します。
国公立大学
センター試験(5教科:7~8科目)と個別試験の総合点数から合否を判断。計算力や知識といった基礎学力を求められることから、すべての科目で点数を取る必要があります。総合的な学力の高さが必要になるため難易度が高い反面、私立に比べて圧倒的に学費が安いという魅力があります。カリキュラムの面では大学院が充実しており、4年生終了後も研究医として学ぶことができます。
私立大学
大学ごとに出題傾向があり、特定の科目に対して深く問われるのが特徴です。志望校を絞って対策を行なうと、効率的に合格に近づけるでしょう。カリキュラムでは臨床医養成に力を入れていることから、医師国家試験の合格率を上げるための対策を行う医学部もあります。
違いを理解して大学を選択しよう
国立大学と私立大学は、入試対策も入学後の流れも異なります。それぞれの特徴を把握し、自分にあった大学を選ぶことが大切です。
試験の配点で決める
国公立大学の医学部は、センター試験の合格点数で2次試験の受験生を選抜します。従ってセンター試験で高得点を取ることが重要。東大の理科三類や京大の医学部医学科を狙うのであれば、センター試験の得点率90%は必要でしょう。旧七帝大(東北・九州・北海道・大阪・名古屋)についても同様です。地方の難関医学部であっても、85%以上の得点率は必須。どの大学にしても国公立の医学部を目指すためには、高い学力が必要です。
センター試験はマークシート方式で、特殊な問題は出ない反面、問題数と計算量はとても多いのが特徴。苦手科目が多いほど、合格が遠のきます。一方、私立医学部では入試問題に一定の傾向があります。中には科目ごとに配点を変えている大学も。自分の得意な科目の点数配分が高い大学を選ぶことで、合格を狙うのも一つの手です。
自分の得意分野で決める
私立大学の選び方によっては、自分の得意分野で勝負することが可能に。物理・生物・化学のうち1科目を選択するタイプの入試であれば、自分の得意な科目に絞って集中的に勉強できます。東海大学と近畿大学では、理科3科目からいずれか1科目を選択するだけで済むため、得意な分野で勝負できるチャンス。数学が苦手で特に数ⅢCが難しい人であれば、帝京大学・近畿大学がおすすめです。帝大・近大の入試では、数学は数ⅠA・数ⅠBだけから出題されるため、勉強量が軽減されます。また、英語が必修である以外は、国語・数学・生物・物理・化学の5科目から2つを選択できる医学部も。
得意科目と不得意科目が分かれている人は、得意科目が選択できる大学を狙いましょう。
地域で決める
近年、医師不足解消のため、政府が医学部の定員に対し規制緩和策を実施。全国の医学部が定員を増やしたため、医学部志願者が急増しました。特に首都圏の医学部は激戦区。首都圏以外の地域と比較して、2倍以上の医学部が存在しています。医学部が集中していることから、同時に複数の医学部を受ける志願者も。結果として首都圏の医学部の受験倍率が年々上昇する傾向にあります。そのことを考えると、地元に近い医学部を優先的に受けるのは一つの選択肢です。
地方の医学部生の主な進路として、その医学部の関連病院が挙げられます。地元の医学部を目指せば、住み慣れた地域に対して医療で貢献できるのです。
住んでいる地域を意識して志望校を決めることも大切ですね。
予備校で相談して決める
志望校選びに迷ったときには、医学部受験を知り尽くしたスペシャリストがいる医学部専門予備校に相談するのもよいでしょう。長年多くの受験生を合格させてきた実績をもとに、カウンセリングから得意不得意を把握。最新の大学情報と照らし合わせて志望校を選定する手助けをしてくれるでしょう。
医学部専門予備校では、医学部の推薦入試やAO入試といった、制度が複雑な入試の傾向もしっかりサポートしています。それぞれの大学の出題傾向を把握しているので、志望校の推薦入試やAO入試について知りたい場合は、予備校に相談して指導してもらうのが効率的でしょう。また、医学部入試に必要な面接や小論文もしっかりと分析し、最新の傾向を把握しています。予備校のカリキュラムには面談・小論文対策を含むところが多いので、志望校の面接の雰囲気や傾向を知りたい人は予備校の授業を受けてみるのもおすすめです。