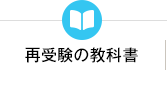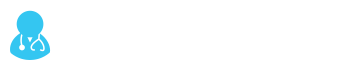医者になるには高校現役合格、または浪人を経て医学部に入学するのが一般的なルートです。しかし他の学部に入学した後で医者になろうと思いなおしたり、いったん社会に出てから医者を志す場合もあります。こうした人でも、もちろん医学部をめざすことができます。最近ではこうした大学在学中または卒業後に、医学部を受験しなおす「再受験」を選ぶ人が増えていると言われています。ここでは再受験の実態について、詳しく解説します。
社会人から医者になる方法
再受験という形で医者になる
社会人や他学部に在学・卒業した人でも、医学部に入りなおす道はあります。一般的に「再受験」と呼ばれ、現役生や浪人生と全く同じ条件で受験することになります。
再受験者の割合
再受験者の人数はここ10年で60倍に増えており、現在ではそこまで珍しいことではなくなっています。社会経験が医療現場でプラスに働くケースもあり、広く門戸を開いている医学部がほとんどです。
現役生徒との扱いの違い
超難関で多浪生も珍しくない医学部受験では、現役生も浪人生も再受験者も、等しく同じ試験を受ける同じ立場となります。再受験者に有利になるような特別枠もありません。体力・集中力・時間の面で有利な若い世代に対抗していくには、同じ勉強方法ではたちうちできないという側面もあります。
再受験という形で医者になる
「再受験」とは、大学を在学中、または大学卒業後に一般企業に就職をしてから、改めて大学を受け直す人のことをさす言葉ですが、ここでは主に医学部を受け直すことを意味します。再受験者はここ10年で急増しており、年間4万人近くが再受験者だと言われています。
再受験者増加の背景には、若い世代の間で資格や免許が必要な職種に人気が高まっており、その中でも一生働けて、収入・ステータス共に最高ランクの医者を目指す人が増えていることが影響しているといわれています。いったん他の学部や社会に出て、初めてわかることがありますし、大学全入時代(大学の入学定員数より入学希望者数が下回る状況)に突入したことで、本当にめざしたい道がわからないまま進学する学生が増えていることも理由に挙げられています。
再受験者は医学部以外の世界を知っているため、より客観的な視点で物事をとらえることができます。特に社会人の場合は社会経験が医療現場で生かされるケースも少なくないため、再受験者を歓迎する医学部もあります。ただし、ストレートで医学部に進む学生に比べると再受験者は受験勉強にさける時間を確保することが難しく、仕事と勉強の両立が最大の問題となります。
社会人の再受験者の割合
とある大手予備校が行った調査によると、医学部をめざす再受験者数は4万人近くにのぼっていて、ここ10年でおよそ60倍という驚くべき倍率で急増しています。大学によっては医学部合格者の1割が再受験者というケースもあるそうです。
超難関の医学部受験の場合、正規入学でも2浪3浪人など多浪の人は珍しくありません。そういう意味では、現役だろうと浪人だろうと再受験だろうと、医学部受験においてはそう違いはないと考えられそうです。
ただし、再受験者は医学部受験に集中できる一般の受験生と違い、どうしても時間に制限があるのがネックです。医学部に合格するには国公立で2000時間、私立でも1000時間は勉強する必要があるといわれます。
時間的に制約があり、年齢的に集中力・記憶力が衰えているなど不利なことも多いため、再受験を受けるには予備校などを上手に利用しながら、効率よく勉強することが重要となります。
現役生徒との扱いの違い
再受験を志願する人は年々増えてはいますが、残念ながら全ての医学部が再受験生を歓迎しているわけではありません。しかも、再受験者に優しいかどうかという大学側の対応については明言しているところはほとんどなく、あくまで口コミや入学者のうち再受験者の割合をチェックしてある程度目星をつけるしかありません。
覚えておきたいのは、基本的に現役生や浪人生より再受験者を積極的に採用する医学部はないということ。医者は一人前になるまで最低10年はかかるといわれる職業ですから、体力・学力が高くて長く医者として働けるという意味では若い受験生のほうが有利といわざるをえません。
ただ、再受験者だからといって弾かれるわけではありません。現役生にも再受験者にも等しく門戸は開いています。そういう意味では、現役生と根本的な扱いの違いはありません。「絶対医者になるんだ」という強い意思と、受験勉強に費やす時間をできるだけ多く捻出する努力、限られた時間で最大限の効果をあげるための戦略的な勉強法を十分に考え、難関である医学部受験にのぞみましょう。
医学部編入とは?
医学部への入学は現役合格か再受験の2つの道が主流でした。しかし、近年では第3の道として「医学部編入」が注目されています。
ここからは、医学部編入の方法や、他の方法との違い、必要な受験科目について開設。また、社会人が医学部に入るために必要なことについてもまとめています。
医学部編入をする方法は?
医学部に編入するには、実施している大学の医学部に、編入学試験の申込みをする必要があります。編入学試験の内容は、年度ごとに内容が変わるため、事前に問い合わせたり、ホームページやパンフレットで確認しましょう。
ちなみに、平成28年度には、国立大学は29校、私立大学の6校で、編入試験が実施されました。編入を希望している大学が、編入学試験を設けているかチェックしておくといいかもしれません。
再受験と医学部編入の違いは?
大学を卒業または卒業見込みの人など条件がある
医学部編入試験が受けられるのは「4年制大学を卒業した人」もしくは「大学を卒業見込みの人」のみです。学士の資格保有者が対象となっています。しかし、一部大学では学士でなくとも受験が可能です。
試験科目は少なめ
編入試験で一般的なのは、英語・数学・化学・物理・生物です。この中から、「英語+生命学」や「英語+数学+理科」などと言った組み合わせで出題されます。科目自体は、センター試験とあまり大差はありません。大学受験を経験しているのであれば、しっかりおさらいすること・問題の傾向を確かめておくことで高得点が狙えるでしょう。
募集人数が少ない
編入試験の特徴の1つが、競争率の高さです。人気のある大学だと、なんと50倍もの倍率になります。というのも、そもそもの募集人数が少ないから。狭き門を争うことになります。
医学部編入のために必要な学力は?
医学部編入のために必要なのは、高校と大学の教養課程を理解できる学力です。
医学部編入の試験は「生命科学系科目」「英語」「小論文」などが第1試験、もしくは第2試験で科されます。合格するには、筆記および面接で高得点を取ることがなによりも重要です。苦手科目があるときは、しっかり対策しておきましょう。
ちなみに、編入試験によく見られる「生命系科目」とは、分子細胞生物学を中心に生化学、神経科学などを合わせた科目です。
医学部編入に向けて医学部予備校でできること
医学部予備校では、試験対策・スケジュール調整・面接対策などが行えます。予備校が各大学の問題や受験者の傾向といった情報を集めてくれるので、1人で受験するよりはるかに多くの情報が手に入るのがメリットです。
また、医学部の編入試験は、5月・6月に9大学、7月・8月には15大学、9月は7大学が試験を行うなど、実施時期が大学ごとに異なります。流動的な情報を集め対策を練るのは1人では大変です。予備校の力を借りて、効率的に試験対策をするのをおすすめします。
社会人から医師になるということ
社会人が医師になる理由
社会人が医者になろうと決断する理由は人それぞれ。ここでは、一度社会に出てから医学部に編入した人の体験談を紹介します。
システムエンジニアから精神科医になりました
新卒で6年務めたIT企業を辞め、医師になりました。高校の非常勤講師として努めていたとき、医学部志望の生徒に小論文を教えていたんです。そこで、私自身が医師という仕事に興味を惹かれてしまい、目指すことにしたのがきっかけです。一般枠で受験して、いまでは医師として働いています。
社会人に寛容な大学は多い
社会人の受験者に対して寛容な大学は多くあります。1つは、学科試験の点数で判断している大学。年齢ではなく純粋な学力のみを見ているので、社会人であっても受験しやすいのです。
2つめは、人柄を重視している大学。学科試験の点数が取れていることが前提ではありますが、社会人としての経験が医師を目指すのに足ると判断されれば、年齢に関係なく合格となります。しかし、そうではない大学もあるので、希望する大学の寛容度を前もって調べておきましょう。
社会人の医学部受験対策
働きながら医学部を目指すのはなかなか大変です。落ち着いている仕事であれば、土日に勉強時間を確保してください。必要であれば有給を使うことも視野に入れましょう。
人によっては、仕事を辞めて勉強に専念するケースもあります。しかし、経済的に難しいことが多く、あまりおすすめはできません。親や配偶者を頼れるといっても、皆がそうできるわけでもないからです。医学部への受験の数年前から貯蓄し、生活費を確保しておくと周りからの心配が少なくて済むでしょう。
社会人の受験支援制度
社会人で医学部を受験しようと、医学部予備校への入学をする人がいます。しかし、学校によっては合格率を保ちたいために断るケースがあるようです。そんなときは、社会人を対象とした受験支援制度を設けている予備校を探すのがおすすめ。授業料の割引や勉強のスケジュール調整、その人に合わせたカリキュラムの制作などをしてくれます。
社会人といえど、医学部受験はゼロからのスタート。しっかりサポートしてくれる予備校を探すことも、合格への近道と言えるでしょう。