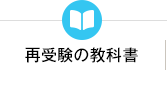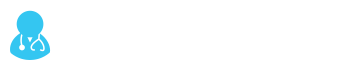医学部合格に必要な戦略。それは、すごくシンプルで、誰しも一度は聞いたことがある故事に表されています。
これは、2500年以上前に書かれた中国の兵法書「孫子」の一節です。勝負を分けるのは、情報に基づく綿密な戦術である、という趣旨の格言ですね。よく医学部受験は情報戦だと言われますが、まさにその通り、情報こそが医学部攻略のカギとなります。
では、なんの情報が必要なのか。
それこそが、孫子に表された「彼=各校医学部の入試傾向」と、「己=自分の学力・性格」に当たります。
彼を知り己を知るための最短ルート


医学部受験は、大学によって出題傾向や得点配分が大きく異なります。そのため、出題傾向を知って集中的に勉強している人と、ガムシャラに試験範囲を勉強している人とでは、合格率も明らかに違ってきます。
また、各校の出題傾向がわかっていれば、志望校を選ぶ際に自分の得意分野と照らし合わせることで、偏差値にビハインドがあってもそれを覆せる可能性すら生まれてきます。
本当にささいな情報の有無が、合否を分けることも十分にあり得るのです。
そういった、質の高い受験情報を得るためにおすすめしたいのが、医学部受験に特化した予備校に通うこと。
<医学部受験に特化した予備校に通うメリット>
- 全国の各医学部の長年の過去問を収集しており、出題傾向も把握している
→彼を知ることができる - 模試や校内テスト等で、自分では気づけなかった得意分野・不得意分野を明確にできる
→己を知ることができる - それまでの合格実績から、自分に最適の志望校を提案してもらえる
→勝算の高いフィールドで戦える
<医学部受験に特化した予備校に通うメリット>
- 全国の各医学部の長年の過去問を収集しており、出題傾向も把握している
→彼を知ることができる - 模試や校内テスト等で、自分では気づけなかった得意分野・不得意分野を明確にできる
→己を知ることができる - それまでの合格実績から、自分に最適の志望校を提案してもらえる
→勝算の高いフィールドで戦える
もちろん、ただ漫然と医学部予備校に通うだけではあまり意味がありません。「彼を知り、己を知る」という明確な目的意識を持った上で、医学部予備校の持つ情報力を活用しましょう。
とくに合格率の高い医学部予備校は、学生の得意分野と各医学部の特性を戦略的にマッチングしているところがほとんどです。本当に必要な分野に「選択と集中」をすれば、短期間でも劇的な成果が出せるはずです。
<戦略的な医学部受験に定評のある予備校>
医学部受験に定評のある予備校を3校を厳選しました。生徒の体験談を読めるページに移動できるボタンを用意しています。予備校の生徒の体験談を読むことは、予備校での受験勉強生活をイメージするのにとても重要です。ぜひ3校の中から気になる予備校の体験談を読んで、自分がその予備校と相性がいいのか見定めましょう。
| 代官山メディカル | メディカルラボ | メルリックス学院 |
 【2020年度合格実績】
98名 |
 【2020年度合格実績】
1,213名 |
 【2020年度合格実績】
221名 |
|
<ここが戦略的!>
●1クラス9名という少人数体制を採用。課題の進捗度など細かい学習管理を行っている
●9段階に分かれたレベル別のカリキュラムで、学力に応じた受験対策を提案
●午前・午後・夜間、それぞれのタイミング毎に、最適な課題を用意している
|
<ここが戦略的!>
●全国に25校展開する情報網を生かし、各医学部の詳細な入試データを収集している
●本来の志望校のほか、生徒の特性にあった受験校も加える受験校決定戦略を完備
●生徒毎の学力と志望校の出題傾向を分析した上で、完全個別指導による学力向上を図っている
|
<ここが戦略的!>
●1クラス9名以下という少人数制を採用。各人の個性を把握し、学力の最大化を図っている
●受験生から入念な聞き取りを行い、推薦入試などあまり表に出ない試験内容も蓄積
●スパイラル方式という、記憶の定着度を高める独自の授業体制を完備している
|
| 代官山メディカル |
|---|
 【2017年度合格実績】
320名 |
|
<ここが戦略的!>
●1クラス9名という少人数体制を採用。課題の進捗度など細かい学習管理を行っている
●9段階に分かれたレベル別のカリキュラムで、学力に応じた受験対策を提案
●午前・午後・夜間、それぞれのタイミング毎に、最適な課題を用意している
|
| メディカルラボ |
|---|
 【2017年度合格実績】
802名 |
|
<ここが戦略的!>
●全国に22校展開する情報網を生かし、各医学部の詳細な入試データを収集している
●本来の志望校のほか、生徒の特性にあった受験校も加える受験校決定戦略を完備
●生徒毎の学力と志望校の出題傾向を分析した上で、完全個別指導による学力向上を図っている
|
| メルリックス学院 |
|---|
 【2017年度合格実績】
287名 |
|
<ここが戦略的!>
●1クラス9名以下という少人数制を採用。各人の個性を把握し、学力の最大化を図っている
●受験生から入念な聞き取りを行い、推薦入試などあまり表に出ない試験内容も蓄積
●スパイラル方式という、記憶の定着度を高める独自の授業体制を完備している
|
相性のいい医学部の探し方


志望校を偏差値や模試の判定結果で決める人は多いですが、実はそこに敗因が潜んでいることも。というのも医学部にはそれぞれ出題傾向に「クセ」があり、同じ偏差値レベルの医学部でも得点配分が違っているからです。
例えば同じ偏差値レベルのA、Bという2つの医学部があるとして、A校の英語の得点配分が200点、数学が100点、B校が英語100点、数学200点の場合、英語が得意な人はA校が、数学が得意な人はB校が有利になります。
物理と生物を選択できる場合は、大学によって物理選択が有利に働くこともあり、科目の選択についても検討次第で得点が期待できます。
また数多くの問題をスピーディに解くのが得意な人はマークシート式を採用している医学部が向いていますし、問題は少ないけれどじっくり考えるのが得意な人は記述式が向いています。
こうした自分の得意分野や教科と、医学部の出題傾向を照らし合わせて、より得点を稼げる「相性のいい医学部」を受験すれば、たとえ模試で合格ラインを下回っていても十分合格できるチャンスはあるはずです。
まずは自分がどんな形式の問題が得意なのか、どの科目、どの分野なら点を稼げるのか客観的に判断した上で、どの医学部を受験するべきか考えてみましょう。
合格体験記のエピソード
- 小さい頃から医師に憧れがあり、中学校3年のときに医師が患者の命を救うシーンを見て、「自分も将来こうなりたい」と強く思うように。それから医学部進学を目指すようになりました。
予備校に通って良かったところは、小論文の対策を行なえる部分です。医学に関する知識やテーマごとの書き方を効率よく習得できたので、本番でも緊張せずに臨めました。模試で悪い点数を取ると、かなりへこみます。そんな時は「たまたま問題が合わなかっただけ!実力はあとからついてくる」と言い聞かせ自分を鼓舞。周りから「受験期は毎日勉強しないといけない」というプレッシャーをかけられていましたが、漫画を読んでストレス解消していました。
受験期はうまくいかないことや辛い思いをする場合が多いですが、勉強し続ける努力は決して裏切りません。最後まで諦めずにやり遂げれば、必ず結果はついてきますので、頑張ってください。 - 小学生の頃に祖母が胃がんにかかり、大手術によって回復したのが医学部進学を目指すきっかけでした。高校2年生のときに進路を考えるにあたり、人々の助けになるような仕事に就きたいという思いから、医師を目指すように。
私が予備校に通って良かったと思う部分は、個別指導で自分の弱点を集中して勉強ができるカリキュラムがあるところです。先生と1対1なので気軽に質問ができるのも良かった部分。また、医学部情報に詳しく、親身になってくれるスタッフの対応も医学部予備校の魅力でした。
受験勉強中は、モチベーションを保つのに1番苦労したのを覚えています。行きたい学校のパンフレットを読んだり、T.A(ティーチング・アシスタント)をお話したりして乗り越えました。
医学部受験では、「絶対にこの大学に行きたい!」という気持ちが大事です。気持ちが途切れたら、行きたい学校のパンフレットを見てモチベーションをあげるようにしてください。 - 高校2年生のときに後輩が脳腫瘍で亡くなり、自分が医師になって、若くして命を落とす子どもたちを助けられたらと思い医学部を目指すようになりました。
私が通っていた予備校は個別指導だったので、自分の学力に合わせて教えてくれるところが良かったです。医学部に在学中の学生から大学生活についての話しも聞けて、モチベーションも上がります。本格的に受験勉強を始めたのは高校2年生の12月頃。受験勉強で苦労したのは、計算ミスを減らすこと。対策として、計算を見直すときに自分が書いた内容だけでなく、もう一度紙に書いて解き直すように努力しました。
受験期はどうしてもストレスが溜まってしまうものです。受験勉強中は座っている時間が多いので、体を動かせないことにストレスを感じるように。ゴルフ部に所属していたので、ストレス発散法としてゴルフクラブを持って素振りをしていました。
人生一度きりの高校生活です。これから受験を控えている学生は、勉強だけして終わってしまったと感じないよう、高校生活を楽しみながら受験勉強に専念して欲しいです。 - 兄が通った予備校に入り、少人数のクラス編成で先生に質問しやすく暖かい雰囲気で過ごせたのが良かったです。また、兄もここで学んで医学部に合格したので、初めから信用していました。化学の偏差値が50台で最後まで伸び悩みましたが、途中で他の教科でカバーすることに方針転換。特に英語は直前まで力を入れる作戦でいき、結果的に偏差値が69.9までアップしました。
努力が実ったなと感じたのは数学です。とにかく概念から理解することが大事だと知り、基礎を何度も繰り返し勉強しました。先生もじっくりと教えてくれたので、おかげで夏までには基礎を完全にマスターできたと思います。
本格的に受験勉強を始めたのは高校2年生の冬頃。長丁場なので夏までの間は週に1日勉強しない日を作りました。ストレスにならない勉強スケジュールを組んだので、息切れすることなく受験生活を送ることができたと思います。また、信頼できる予備校に入ることで安心して受験に向き合えたと実感しています。ぜひ早い段階で無料説明会や体験会、在学生から評判を聞くなどして信頼できる予備校を見つけてください。 - 浪人して医学部に合格しました。もともとは理系の研究職を目指していましたが、現役生のときに研究機関の方とお話できる機会があり、研究職にとって医師としての知識や経験は大きなアドバンテージになると知ったのです。それきっかけで、高校3年生の夏ごろから医学部受験を意識し始めました。
入試情報は予備校とネット情報を利用。おかげで十分な戦略を立てることができました。苦手科目以外で点数を稼ぐ方法もありますが、自分は一番努力した苦手科目に救われたと感じています。どの学生も学力が高い中、得点数が低い科目があると平均点は伸びません。苦手科目を底上げできたことが合格につながりました。
普段の過ごし方で意識したのは気分転換です。睡魔に襲われるとわざと外で参考書を読む、短時間ならいっそ寝てしまうことですっきりしました。
長い受験生活、辛いときには気分転換をはかりながら、「楽しい!」と自分に暗示をかけることも必要です。一生のうちで勉強だけに没頭できる時間はそう多くはありません。伸び悩むことがあってもぜひ楽しんでください。 - 父親が医師なので身近な職業でした。宮城県出身で東日本大震災を経験し、被災現場での医療行為を見たこと、父親がほとんど帰宅せずに現場で働く姿を見て、医術の大切さを痛感し一念発起。勤めていた会社を退職し、受験生活に突入しました。
予備校には受験校の選定でいろいろな情報がもらえます。学卒性を受け入れる大学と受け入れない大学があることを初めて知りました。12時間指導を謳った予備校ですが、当時自分は12時間勉強することが辛いとは思わなかったです。先生方はそれ以上の時間をかけて学生と付き合ってくれたので、とても充実した1年でした。
努力した点を挙げるとすれば、社会人になったあと勉学から離れていたこともあり、特に数ⅢCにはなじみがなく、基礎をしっかりやり直したことです。化学もこんな基礎からやるの?と思うくらいの基礎からやり直しました。
再受験というのは受験できる大学が減る分逆風だと言えます。中途半端な覚悟では必ず失敗するでしょう。背水の陣で向き合う必要があるので、本気でやりぬく覚悟があるかしっかり考えてください。そのこだわりぬいた決意があれば、きっと合格できます。 - 高校1年で中退したあと、4年間アルバイト生活をしていました。だんだんと焦燥感にさいなまれ始め、人生を真剣に考え始めたとき、父親が医師だったということもあり医学部への進学を目指すように。
予備校の先生から、高卒認定でも差別がなく試験傾向が自分に合っている大学を選んでもらいました。入試情報に強く、自分のことをよく理解してくれている先生に指導してもらえるのが、最大のポイントだったと思います。
高校には半年しか行ってなかったので、本当にわからないことだらけでした。先生が何をどうやればいいのか、順番まで考えてくれたので信じてその通りに実行。毎日12時間の勉強時間はストレスに感じる暇もなく、勉強に打ち込めたのはクラスメイトの存在でした。
濃密な受験生活で、自分のレベルや状況をよくわかってくれる先生に出会いアドバイスを素直に聞いて、医大合格に必要なことだけをやったので合格できたと思います。 - 予備校に入ったのは高校3年生の夏で、部活動を引退してやっと受験に向けて意識が出たときでした。もともと部活動と並行して塾には通っていましたが、成績は伸び悩んでいたので医学部専門の予備校に入学。
少人数のクラスで質問の取りこぼしがなく、担当の先生以外も真剣に教えてくれるので、自習中でも気軽に質問できたのが良かったです。
予備校で特に努力した教科は化学。学校の授業は進みが早すぎて理解できませんでしたが、予備校で丁寧に学ぶことができたので苦手科目にならずに済んだと思います。
時間の使い方には工夫しました。英単語や歴史といった暗記ものは移動時間を利用し、1日のタイムスケジュールを勉強時間・休憩時間・その他(食事・入浴・睡眠など)の単元に分けて、メリハリをつけて過ごすように意識。
受験期は努力が結果に結びつかなくて焦るときもあります。でも、自分を信じて努力し続けることが医学部合格の近道です。結果に一喜一憂せず、基礎を大事に頑張ってください。 - 本格的に受験勉強を始めたのは高校2年の2学期でした。センター試験対策を考えると、3年の8月までには基礎を固めておかないといけないので、集団授業と個別授業を並行して受けて、とにかく基礎固めに没頭。自宅は勉強できる環境ではなかったので、とにかく毎日予備校に通いました。朝9時から夜の9時まで勉強し、その代わり家では1時間以上は勉強しないという生活リズムに。しっかり睡眠と食事をとり、遅刻しないことが体調管理に役立ったと思います。
勉強が辛くなったなと感じたときは、先生やスタッフの方と世間話や悩み相談をすることでリフレッシュ。おかげでスタッフさんとも仲良くなれました。
特に力を入れたのは復習です。なぜ間違えたのか?何を誤解したのか?ミスした内容を把握し次に活かすことが大事だと考えました。
長い受験生活は自分との闘いです。伸び悩んでいる時期に先生にきついことを言われるとしんどいですが、それでも塾に行ってください。続けて勉強することが、きっと良い結果につながります。 - 2浪して医学部に合格しました。予備校は先生方の授業がわかりやすかったのが決め手となり入学。英語の得点が伸び悩み、後期では英語のクラスのランクを落とされました。それがきっかけで一念発起することに。
3月から7月までは基礎力固めに費やし、8月は予備期間、9月以降は過去問を徹底的にこなして弱点を克服。授業がない日も自習室で勉強するほか、日曜日には友人と過去問を解きあうなど、一人だけで頑張るのではなく励まし合いながら頑張りました。
悩んだときには先生にすぐに相談できるのが予備校の魅力です。先生は受験に関してノウハウがあり、親身になって指導してくれるので必ず結果に結びつきます。
志望校を決めるにあたり、公立か私立か悩む時期があるかと思います。「私立専願だから」と言ってセンター試験対策をしないと後悔することになるので、しっかりと志望校を定め、最後まで諦めないで頑張ってください。