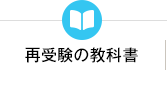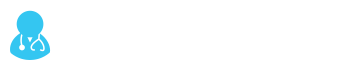私立医学部の志願者数がついに10万人を突破し、一般入試の難易度の高さや半数に満たない現役合格率の低さ、医学部受験者の多浪化が年々加速している医学部受験。熾烈な一般入試を勝ち抜く以外に、何か方法はないだろうかと考えるのは当然でしょう。
全国の国公立や私立の中には推薦入試やAO入試を実施している医学部もあり、一般入試より倍率は低めなのが一般的です。ただし、医学部に適性がある生徒だけが合格できるため、一般入試とは違う意味でシビアな面があります。
医学部受験の方式について
国公立の推薦入試
国公立医学部では多くの大学が推薦入試を導入しており、一般入試に比べると倍率は低いと言われていますが、受験資格にトップレベルの学力が求められるため、決して楽な道とはいえません。
私立の推薦入試
私立大でも推薦入試を採用している大学がありますが、国公立同様高いレベルの学力が求められます。また大学によって入試内容が大きく異なるため、志望校に合わせて入念な準備が欠かせません。
AO入試
国公立や私立では推薦入試のほかに、AO入試を導入している大学がいくつかあります。しかしその数は非常に少ないため狭き門といえます。学力以外の入試科目が資質を見極めるため特殊なケースが多く、その内容はもちろんどの大学も公開はされていません。
国公立の推薦入試
国公立の大半は公募制推薦を採用しています。2015年度は東京大学医学部が初の推薦入試を導入し、大きな話題となりました。また、地方の大学では地域の医師不足を解消するための処置として、「地域枠」や「地域医療特別枠」などの名称で特別推薦枠を設けているところもあります。浪人でも受験可能な大学も一部あります。
超難関といわれる一般入試に比べると、国公立の推薦入試はおおむね倍率が低いのが特徴です。ただし、それはあくまで推薦枠に応募できる人材自体が限られているためで、ほとんどの大学では高校の成績がA~E評価であればAランク、5段階評価で4.3以上であることが受験資格となっており、この時点で多くの志望者が振り落とされます。
また応募できたとしても一般入試と同等の学力が求められ、センター入試の受験が定められている大学も多いため、一般入試にも対応できるだけの高い学力を身につけておく必要があります。
国公立の推薦入試は大学によって入試科目に差があり、小論文や面接、記述・論述式の試験など、推薦用に対策が必要な内容であることがほとんどです。特に面接は必ず行われますので、志望校についてしっかり学習し、志望動機を自分の言葉でしっかり語れるようトレーニングしておくことが必要です。
私立の推薦入試
私立大の医学部では指定校推薦、公募制推薦、地域枠推薦などが利用できます。私立の推薦入試で求められる成績は、国公立ほど厳しくはありませんが、それでも5段階評価で4以上という大学が大半を占めています。基礎学力が高いことは大前提となります。
推薦入試では英語、理科、数学を中心に、大学によっては一般常識問題なども出題されます。マークシートや選択問題は少なく、記述式を採用している大学が多い傾向があります。過去問などもほとんど出回らないため対策が難しく、基礎的な問題を記述式で明確に答える訓練が必要でしょう。
また小論文と面接は、ほぼ必須と考えたほうが妥当です。中にはグループ討論が行われる大学もありますので、自分の考えをしっかりと発言できるスキルが求められます。国公立同様、志望校に対する理解や、どんな医者になりたいのかといった将来の展望などを質問される可能性が高いので、それに向けて準備が必要です。私立については情報量が少ないため、医学部専門予備校などで情報を入手するのも1つの方法といえます。
AO入試について
推薦入試に比べると、AO入試を実施している医学部の数は国公立が10校、私立が2校と、極端に少なくなります。若干名の募集から40名近い募集まで大学によってさまざまで、地域枠を設けている大学もあります。
AO入試については受験内容が特殊なことが多く、その内容についてはほとんど公表されていません。ただしAO入試は大学が求める学生像(アドミッションポリシー)に基づいて、学力を含めてさまざまな角度から選抜される入試です。募集趣旨を理解して、自分がいかに大学の求める学生像に合っているかどうかをアピールできるかが、合格の鍵を握っています。
もちろんセンター試験で高得点が見込める基礎的な学力は必須です。小論文や英文読解力、コミュニケーション能力をはじめ、リーダシップや探求心など、学生の規範となるような優れた学生が求められます。1次・2次試験としてセンター試験の受験が課せられる大学もありますので、AO入試をめざすとしても受験勉強は念入りにしておきましょう。
難関の医学部受験に合格するには?
医学部合格のための考え方
医学部を一般入試で受験する前に、まず知っておくべきことの1つが「難易度の高さ」です。理由としては受験科目の多さと内容の難しさがあげられます。そのだいたいは、英語・数学(123AB)・理科(化学、物理、生物から2つ選択)です。国立大学の医学部だと、加えてセンター試験の5教科9科目を勉強する必要があります。すべて習得するには短期間の対策ではなく、長期的に計画して勉強し続けなければなりません。また、合格するためには何を勉強するべきか、効率の良い勉強方法、時間を明確にすることも大切です。早い段階での対策が必要になるでしょう。
医学部合格のためのスケジュール例
医学部に現役で合格するためには、高校1年生から計画的に勉強しましょう。まず大切なのは基礎知識を身につけること。1~2年生で基礎知識を身につけたら、高校3年には過去問題や応用問題などに取り組み、どんな問題にも対応できるようになるのがベストです。
難関大学の医学部に一般入試で現役で合格した受験生のスケジュール例をみてみましょう。
高校1年生
数学・英語の基礎問題を徹底的に身につけます。
高校2年生
数学・英語の1年生で身につけた基礎をもとに応用編や上級編に取り組みます。加えて化学・物理・生物の基礎力や応用問題を勉強します。
高校3年生
4~8月にかけては基礎問題とこれまでやってきた問題集の総復習に加え、応用問題に挑戦。国語・社会の勉強も始めます。9~12月はこれまでの総復習と過去問題などに取り組み、1月2月のセンター試験と二次試験を受験します。
国立医学部に合格する方法
国立医学部の受験対策は?
同じ医学部でも私立大学に比べ授業料が安い国立大学は、大学ごとの2次試験とは別にセンター試験対策が必要です。勉強する科目が増えるため難易度もアップ。また、合格した受験生のほとんどが、センター試験で9割以上の点数を取っています。偏差値も高く勉強量も多くなるので、効率の良い学習が大切でしょう。国立大学医学部の合格者数は大手予備校が多いようです。
一方、医学部専門予備校は受験科目が絞られるため、比較的に私立大学医学部の対策に特化しています。センター試験は他の学部と同じ対策が必要なため、やはり実績のある大手予備校がおすすめです。ホームページや相談会などで多くの合格者を出しているか調べて、問い合わせるとよいでしょう。
センター試験対策の大切さ
国立大学の医学部は、二次試験にプラスでセンター試験対策が必要です。どっちか片方だけでなく、どちらもしっかり学習しなければ合格するのは難しいでしょう。まずは二つに共通する科目である英語・数学・理科を徹底的に勉強し、高得点が取れるようにするのが大切です。
センター試験に失敗すると二次試験を受けることはできないので、確実な対策が必要。文系の科目は二次試験では必要ないものの、暗記するものが多いため、短期間で覚えて高得点を狙えます。こちらもセンターでは大切な要素なので、しっかり勉強して点数を稼ぎましょう。
私立医学部に合格する方法
国立大学との違いを理解する
私立に比べて学費の安い国立の医学部ですが、難易度は高く総合的な学力の高さが必要です。一方私立は学校によって受験科目や出題の傾向に特徴があります。そのため少ない科目で受験できるので、負担は少ないといえるでしょう。しかし、近年私立医学部の志願者数は増加傾向にあります。
国立に比べ受験者数もより多く、人気の大学では1,000人を超えるというところも。倍率の高さは国立大学に比べて、2倍以上に及びます。また、毎年のセンター試験の難易度や入試の日程、前年度の倍率などによっても倍率に変化があるようです。
自分の得意分野で受験する
総合的な学力に自信がある場合、国立・私立の両方を受験するのもよいでしょう。しかし、現在の学力などに不安がある場合、無理して両方を目指すよりも私立大学に絞るのも1つの手。センター試験が必要な国立大学は、当然勉強する範囲や求められる学力も多くなります。
一方、私立では大学によって入試科目も違うため、国立医学部入試でしか出題されないような問題はあまり活かされません。確実に医学部に合格したいのであれば、まずは自分の得意分野の科目を活かせるような私立大学を探すことがおすすめです。志望校に合わせて受験対策ができ、合格へと近づけるはずです。