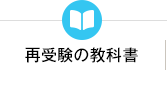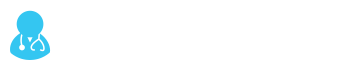医学部の受験科目を紹介
医学部の受験科目は、他学部と違う傾向にあります。同じ医学部でも国立大学と私立大学、どこの私立大学を受けるかによっても受験科目が変わることも。こちらでは、医学部に入るために必要な科目を詳しく紹介していきます。
医学部受験の科目について考えよう
国立と私立の違い
国立大学の医学部と私立大学の医学部の受験科目は大きく異なります。国立大は受験する科目が多いですが、一方の私立大学は科目数が少ない傾向に。それぞれの受験科目について詳しく説明していきます。
センター試験の科目
国立大学の受験に必要あるセンター試験の科目は、英語・数学・国語・社会・理科の5教科7科目が必須。医学部で受けるべき、7科目の内訳を紹介していきます。
小論文や面接
医学部受験は、ほとんどの大学で面接・小論文が設けられています。面接や小論文は多くの方が後回しにしてしまう人も多くいますが、とても重要な試験科目です。どのような問題が出されるのか、解説していきます。
国立と私立の違い
国立大学はセンター試験の5教科7科目を受験するのが基本。次の二次試験では、前期と後期日程に分かれます。前期日程は、英語・数学・理科2科目に加え、面接が設けられています。東京大・京都大・名古屋大などは例外として国語も追加されているようです。
理科は物理・生物・化学の3科目から2つ選択できますが、大学によっては物理・化学が必修となっていることもあるので、事前に調べておいてください。ちなみに群馬大・金沢大・九州大・愛媛大などが当てはまります(2019年度入試前期日程)。このように国立大学は幅広く網羅的に勉強する必要があるようです。
一方の私立大学は、一般入試試験またはセンター試験を利用する2種類のパターンが用意されているケースがあります。一般入試では英語・数学・理科2科目に加え、小論文・面接があります。理科は物理・化学・生物から2つを選択するのが基本ですが、大学によって「理科1科目のみ」や「小論文・面接なし」のところもあるようなので、事前に確認しておきましょう。このように、私立大学は科目が絞られています。しかし問題の内容が深く、高得点を狙わなくてはなりません。また、各私立大学によって出題傾向も変わるので、自分が得意な出題パターンの大学を受けるとよいでしょう。
センター試験の科目
国公立大学の医学部で受けるセンター試験は、基本的に5教科7科目。内訳でみると、英語1科目・国語1科目・数学2科目・理科2科目・社会1科目となっています。
国語は現代文の評論と小説で2題、古文1題、漢文1題で構成されています。
外国語は「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」の5つから選択。ほとんどが英語を選ぶ傾向にあります。
数学は「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」「工業数理基礎」から2科目選ぶ形になります。
理科は「物理」「化学」「生物」「地学」に加え、2015年から受験科目に追加された「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の8科目を用意。その中から2科目選択します。大学によっては必須科目が設定されていることもあるようなので、事前にチェックしておきましょう。
社会は、地理歴史の分類「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」と、公民の分類「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理,政治・経済」の合計10科目から1つを選択します。
小論文や面接
医学部の二次試験で設けられているのは、主に小論文や面接です。この2つの試験で医師にふさわしい責任感や資質をもっているのかを判断。センター試験や一般入試で一定水準の点数を取ることは大事ですが、面接や小論文で、適性でないと判断されれば、医師への道は閉ざされてしまいます。
医学部の小論文は主に「テーマ型」「文章読解型」「資料分析型」の3つに分けられます。
テーマ型は「~について述べなさい」という指示に対して、自分の考えを述べていきます。提示されたテーマに対して予備知識がないと、点数を稼ぐことは難しいでしょう。その状態を防ぐには、新聞やニュースで取り上げられている時事問題を把握しておく必要があります。
文章読解型は、「ある主題に対して見解の述べる問題」または、「要約・説明を求められる問題」があります。課題文のテーマは、医療全般から、自然科学、現代社会論、人間科学系などが多く出題。資料分析型は図やグラフなどを読み取り、それについて見解を述べる問題があります。高齢化や人口動態、感染症の死亡率などのデータが多く出題されている傾向にあるようです。
医学部の面接では、主に「医学部を志望する理由」「本学を志望する理由」「理想の医師像について」「高校生活について」などについてよく聞かれる傾向に。他の受験生とは差をつけるような個性的な回答は求められておらず、どちらかというと無難な回答が求められます。面接にはあまり時間をかける必要なないですが、「医学部を志望する理由」や「本学を志望する理由」は、特にすらすら答えられるようにしておいてください。
知っておきたい診療科目のこと
専門を決める
医師国家免許を取得した後、見習い医師として2年間の研修期間を終えると、いよいよ診療科を絞って専門性を高めていくことになります。ではいつ、どんなプロセスで専門を決めるのでしょうか?専門を決めるポイントを紹介していきます。
専門医の取得
多くの診療科の中から1つの科を専門として選んだら、専門分野をさらに掘り下げるために研鑽を重ね、専門医の資格を取得するのが一般的です。ここでは専門科の選定から専門医を取得するまでのプロセスを紹介します。
人気の診療科目
医者といっても、どの診療科や勤務地を選ぶかによって、生活スタイルや収入は大きく変わります。緊急事案が少なく安定している科があれば、常に生死に関わる難しい症例に携わるハードな科もあり、人気に差があるのが実情です。
専門を決めるタイミング
医者といっても内科や外科、産婦人科、小児科、眼科、脳神経外科、循環器科、消化器科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科・美容外科、救急・ICU、麻酔科・ペインクリニックなど、多種多様な診療科があります。医学部では将来どの科に進むかに関わらず、全ての診療科を学ぶことになりますし、卒業&医師国家免許取得後の初期研修期間として、各診療科を2年間かけて回り、臨床現場で実地経験を積むことになります。
通常、この初期研修にさまざまな診療科の現場を経験することで各科のイメージをつかみ、自分がどの診療科を専門に向いているのかなど、適性を見定めていくのが一般的です。だいたい研修2年目には専門を決める人が多いようです。その上で、専門科の知識と経験を身につけるため3年目以降は後期研修に進み、専門科の指導医について経験を積みます。この際に出身大学の医局に入るか、他大学の医局に席を置くか、医局に入らず市中病院でキャリアを積むかも選択します。
専門医の取得について
専門医とは、特定の診療科で専門医療を提供できる十分な知識と技能、経験を持った医者のことを指し、各診療科の学会が定める5年以上の専門研修を受け、資格審査と試験に合格すると資格を取得することができます。
専門を決めると、まずその診療科の学会によって定められた「認定医」の資格を取得するのが一般的です。指定病院での勤務や学会・講演会の出席回数、筆記・実技試験にパスすると、認定医として認められます。多くの場合、後期研修期間中に認定医を取得するケースが多いようです。
さらに高度な技術と専門知識を身につけた認定医は、専門医としてステップアップを目指します。専門医は内科や外科など、各科のほかに、血液や消化器、腎臓などの部位ごと特化した医師や、脳卒中・結核などの病気に特化した医師、漢方・抗加齢・臨床遺伝・レーザーなど治療方法に特化した医師まで、さまざまな専門医が存在します。そのため自身のキャリアを積むために、複数の専門資格を取得する医者も少なくありません。
人気の診療科目について
医者として多くの患者を救いたい、という気持ちはあるものの、医者も人間ですからやはり激務が続く現場などはできるだけ避けたい、というのも本音だと思います。実際のところ、当直や緊急対応など時間に追われる現場や、慢性的に激務になりがちな診療科を選ぶ医者は少なく、定時勤務で肉体的・精神的な負担が少なく、医療ミスや訴訟問題に発展することが少ない診療科に人気が集まるのが現状です。
比較的緊急対応が少なく、安定した勤務体制が見込める診療科として眼科や皮膚科、麻酔科、泌尿器科などが人気が高いようです。特に眼科、皮膚科、精神科などは訴訟が起きにくい上に、開業しやすい診療科として人気が高まっています。ただし、安定している反面刺激が少なく、激務でもやりがいのある仕事がしたいという人は、内科や外科をめざすケースが多いようです。厚生労働省の調査によると、診療科のうち内科が最も医師数が多く、次いで整形外科、小児科医となっています。
逆に人気が低いのは産婦人科なのだとか。容体の急変が多い緊急性の高い現場で、常に生死に関わるため責任も大きく、結果として訴訟を起こされるケースも多いことから、どの病院でも医師不足に悩まされています。