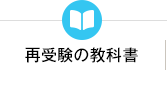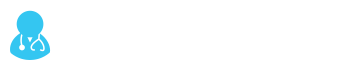医学部の実習ではどのようなことが行われているか知っていますか?大学病院にかかったことのある方は、診察の際に医学生が見学、参加していた経験のある方もいらっしゃると思います。
ここでは、医学部で行われる実習についてを低学年~中学年で行う基礎的な実習と、高学年で行う臨床的な実習に分けて、具体的な内容に触れながらご紹介していきます。
医学部での実習とは
 医学部で行われる実習は、1~4年生と5,6年生で大きく異なります。低学年のうちは、解剖で人体の構造を学んだり、学生同士で採血や診察の練習をしたりと、患者さんを相手にする際に必要な知識の習得や手技の練習を行います。 この他、マウスを用いて実験を行ったり、検体から特定のタンパク質あるいはDNAを検出する方法など、研究や診断に必要な手技も学びます。
医学部で行われる実習は、1~4年生と5,6年生で大きく異なります。低学年のうちは、解剖で人体の構造を学んだり、学生同士で採血や診察の練習をしたりと、患者さんを相手にする際に必要な知識の習得や手技の練習を行います。 この他、マウスを用いて実験を行ったり、検体から特定のタンパク質あるいはDNAを検出する方法など、研究や診断に必要な手技も学びます。
低学年~中学年では座学中心で、週に何度がこれらの実習日が設けられているのに対し、5,6年生で毎日が病院内での実習になります。病院内では1人の学生に対し複数の医師が指導に付き、医師と行動を共にしながら実際の医療現場を学ぶ実習となります。
実習では実際に何をするのか
 低学年で肝となる実習は「解剖実習」です。4,5人で班を作り、数ヶ月かけてご献体を解剖していきます。まず皮膚を剥がすところから始まり、そのすぐ下にある脂肪の中から血管や神経を1つ1つ同定します。脂肪を取り除いたら、さらに下にある筋肉を付着部位を確認しながら切り、その奥にある筋肉や臓器を隅々まで観察していきます。医学部生が初めてメスを手にする実習となります。
低学年で肝となる実習は「解剖実習」です。4,5人で班を作り、数ヶ月かけてご献体を解剖していきます。まず皮膚を剥がすところから始まり、そのすぐ下にある脂肪の中から血管や神経を1つ1つ同定します。脂肪を取り除いたら、さらに下にある筋肉を付着部位を確認しながら切り、その奥にある筋肉や臓器を隅々まで観察していきます。医学部生が初めてメスを手にする実習となります。
この他の実習としては、学生同士で採血をし合ったり、その血液を使って血液型を調べる検査を学んだり、あるいはマウス、ラットなど動物を用いた実験として、解剖や薬剤投与による行動変化の観察などを行います。
病理実習では、実際に顕微鏡を用いて病気のある方から得た組織を観察し、どこにどのような病変があるか、またその所見から病名を診断する方法を学びます。 細菌学の実習では、実際に自身の口腔粘膜や尿、便を採取し、特殊な培地を用いて病原体を繁殖させた後、染色を行って、病原菌の特徴から菌を特定する手技を学びます。
5年生の実習
5,6年生で行う実習は通称「ポリクリ」と呼ばれています。5年生の実習は4,5人ほどで班を作り、1,2週間ごとに大学病院内の全ての診療科を回る臨床実習です。大学によっては、4年生の夏あるいは冬頃から始まるところもあります。これまでの実習とは大きく異なり、学生同士ではなく実際に患者さんを相手に実習を行います。あくまで学生であるため、患者さんに対する行動1つ1つに医師の許可、指導が伴います。
実習内容として、外来での実習では、初診の患者さんであれば、病歴(どのような症状がいつからあるか)や既往歴(これまで患者本人が患ったことのある病気)、家族歴(これまで患者の家族が患ったことのある病気)、内服薬など、診断や治療の方針を決めるのに必要な情報を聞きます。その他、心臓や肺の音の聴診や、お腹の中にできものがないか触診を行うこともあります。実際に診察には参加せず、医師の診察を見学するのみの場合もあります。
病棟での実習では、入院患者さんの診察を行います。ほとんどの診療科では学生1人1人に担当患者さんが割り当てられ、その患者さんについてこれまでのカルテからどのような病歴に対しどのような治療を行っているか、これからどのように治療を進めていくかを学びます。担当患者に関しては毎日診察を行い、カルテを記載して指導医の添削を受けます。担当患者以外であっても、検査や処置などのイベントがあれば見学します。このとき、採血や消毒、包帯の交換、外用薬の塗布など、比較的安全な処置であれば医師の指導のもと学生が行うこともあります。この他、医師全体で入院患者について検討するカンファレンスにも参加し、担当患者についてプレゼンテーションを行います。
外科系の診療科であれば、手術にも参加します。手術は少し離れたところからの見学が主ですが、実際に手術着を着て清潔な手袋をつけ、手術台のそばで見学することもあります。このとき、治療に支障をきたさない範囲での皮膚の切開や電気メスの使用、終盤での縫合やステープラー(ホチキスのように皮膚を留め合わせる機器)など、安全な操作であれば、医師の指導のもと学生が行うこともあります。
6年生の実習
6年生(あるいは5年生の後半)の実習は、5年生の実習の延長です。5年生(早い大学では4年生)から1年ほど全科に渡ってポリクリを行った後、その中から興味をもった診療科を選択し、さらに半年ほどかけてその診療科の実際の現場を学びます。このため、5年生で行う必修実習に対し、選択実習と呼ばれています。
必修実習では、所属する大学病院内での実習がメインとなっていましたが、選択実習では、学生の実習に協力している外の病院で実習を行うことも可能となります。学生という立場は変わらないので、患者さんに対して行える医療行為は変わりませんが、医師・学生ともに“興味があって選択した”という認識があるため、見学のみでなく参加する機会は増えます。同じ理由で、休日であっても急患が来れば呼び出しがあったり、当直の様子を体験するなど、同じポリクリであってもより濃密な実習になります。
まとめ
 基礎的な実習であれば時間割の中での実習になりますが、ポリクリは丸1日の実習が1,2年続きます。実習時間は診療科によって異なりますが、9時集合で17時に解散になる日もあれば、朝7時前にカンファレンスが始まる日もあり、手術が長引けば帰宅が夜中0時を超えることもあります。
基礎的な実習であれば時間割の中での実習になりますが、ポリクリは丸1日の実習が1,2年続きます。実習時間は診療科によって異なりますが、9時集合で17時に解散になる日もあれば、朝7時前にカンファレンスが始まる日もあり、手術が長引けば帰宅が夜中0時を超えることもあります。
身体的にも精神的にも厳しい実習となりますが、仕事中の医師のもとで実際に患者さんを相手に勉強させていただく立場であり、教科書と実際の現場のギャップを埋め、卒業後医師として活躍するためには、避けては通れない修行となります。